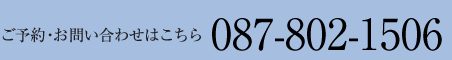当事務所の代表弁護士、八木俊則が下記のラジオ番組に出演します。
FM香川「あなぶきホームの『It's My Home Party』」
2013年1月12日(土)12:30~
http://www.fmkagawa.co.jp/pc/Library/event/anabuki/
平素より当事務所に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
当事務所の年末の業務は12月28日(金)まで、年始の業務は1月7日(月)よりとさせていただきます。
皆様方におかれましてはよき年末年始を過ごされますようお祈りいたします。
アメリカ証拠法研究、今日から関連性(relevance)の解説に入ります。
|
第4章 関連性とその制限 第401条 証拠が関連性を有するための要件
証拠は、次の要件のいずれもが満たされた場合に、関連性を有する。 第402条 関連性のある証拠の一般的許容性
関連性のある証拠は、次のいずれかにおいて別段の定めがある場合を除き、採用可能である。 関連性のない証拠は、採用してはならない。 |
我が国の刑事訴訟法の一般的な考え方では、「関連性」は「自然的関連性」と「法律的関連性」からなるとされています。「自然的関連性」とは、一般に、当該証拠が要証事実(の存否)を推認させる最小限度の証明力を有する蓋然性をいうとされます。また「自然的関連性」がある場合であっても、裁判所による証明力の評価を誤らせる危険を類型的に有する証拠は、「法律的関連性」がないとされます*。
これに対し、連邦証拠規則上は、上記の「自然的関連性」に(おおむね)相当するもののみを「関連性」(relevance)と呼び、この意味での「関連性」が認められる証拠は原則としてすべて採用可能であることが明らかにされています(第402条)。
その上で、日本の「法律的関連性」(に相当するもの)が認められない証拠は、次々回以降に扱う第403条以下において証拠能力を否定する形をとっています。
なお、連邦証拠規則における「関連性」(relevance)が認められるためには、証明力(probative value)(第401(a)条)と、重要性(materiality)(同(b)条)の両方が必要とされます。
したがって、例えばある「証拠」について、ある「事実」を証明するための証明力が高くとも、当該「事実」が訴訟の対象となっている請求の当否を決するに当たって重要でない場合には、当該「証拠」は関連性が認められず、証拠排除されます。
ちなみに第401(a)条の「証明力」に関する規定の文言は非常によく練られており、次回は同条についてさらに解説をします。
*代表的な考え方をまとめた近時の文献として、たとえば出口博章「尋問の関連性について」判タ1318・35(2010)など。なお、最近出された最判平24・9・7(最高裁判所ウェブサイト掲載)では、「自然的関連性」という用語を用いる一方、「法律的関連性」という用語は用いられていません。
|
ARTICLE IV. RELEVANCE AND ITS LIMITS Rule 401. Test for Relevant Evidence
Evidence is relevant if: Rule 402. General Admissibility of Relevant Evidence
Relevant evidence is admissible unless any of the following provides otherwise: |
アメリカ証拠法、これまで導入的な記事をアップしてきましたが今日から具体的な条項に入ります。まずは連邦証拠規則の適用範囲を定める第1101条から。
|
第1101条 この規則の適用範囲
(a) 裁判所および裁判官
(b) 訴訟および手続 (c) (略)
(d) この規則(特権に関するものを除く。)は、次の場合には適用されない。 (e) (略) |
日本の実務家が着目すべきポイントは、連邦証拠規則が(i)陪審員裁判であるかどうかにかかわらず適用されることと、(ii)民事手続にも適用されることでしょう。
(i) 陪審員裁判であるかどうかにかかわらず適用されること
前回の記事で、米国では事実認定が陪審員の専権であることが、米国証拠法の最も大切なバックグランドの一つであると説明しました。
しかし米国でも、例えば刑事訴訟で被告人が陪審の権利を放棄した場合、または民事訴訟で当事者双方が陪審の権利を放棄した場合などには、職業裁判官が事実認定を行いますが(「bench trial」)、この場合でも連邦証拠規則は陪審員裁判の場合と同様に適用されます。
ただ英米法でも伝統的には、証拠排除の法則を職業裁判官による事実認定の場合に用いることが不適当だという考え方はあったようで、現代でも職業裁判官のみによる裁判の場合には、排除法則は陪審員裁判の場合に比べやや緩やかに運用されているようです(以上につきMcCormick113頁)。
(ii) 民事手続にも適用されること(第1101(b)条)
我が国の民事訴訟法では、原則として証拠能力に制限はなく、例えば伝聞証拠であっても当然に排除されず、裁判官の自由な心証に委ねられることになります*。
しかし米国では、民事訴訟にも陪審制が導入されてきたこと等との関係で、民事訴訟においても連邦証拠規則が適用されます。
ただし、個別の条項の中には、刑事訴訟にのみ適用があるもの(例:第404(a)(2)条)、民事訴訟にのみ適用があるもの(例:第412(b)(2)条)などがあります。
*たとえば最(二)判昭和27年12月5日民集6・11・1117。
次回は「関連性」(第401条~)です。
|
RULE 1101. APPLICABILITY OF THE RULES
(a) To Courts and Judges. These rules apply to proceedings before:
· United States district courts;
· United States bankruptcy and magistrate judges;
· United States courts of appeals;
· the United States Court of Federal Claims; and
· the district courts of Guam, the Virgin Islands, and the Northern Mariana Islands.
(b) To Cases and Proceedings. These rules apply in:
· civil cases and proceedings, including bankruptcy, admiralty, and maritime cases;
· criminal cases and proceedings; and
· contempt proceedings, except those in which the court may act summarily.
(c) Rules on Privilege. The rules on privilege apply to all stages of a case or proceeding.
(d) Exceptions. These rules — except for those on privilege — do not apply to the following:
(1) the court’s determination, under Rule 104(a), on a preliminary question of fact governing admissibility;
(2) grand-jury proceedings; and
(3) miscellaneous proceedings such as:
· extradition or rendition;
· issuing an arrest warrant, criminal summons, or search warrant;
· a preliminary examination in a criminal case;
· sentencing;
· granting or revoking probation or supervised release; and
· considering whether to release on bail or otherwise.
(e) Other Statutes and Rules. A federal statute or a rule prescribed by the Supreme Court may provide for admitting or excluding evidence independently from these rules.
|
開業後の雑務と案件に忙殺され、前回のポストから1か月が経ってしまいましたが、米国証拠法の解説を再開(?)したいと思います。
日本の実務家の立場から米国証拠法を観察する際の最も重要なポイントの一つが陪審制でしょう。
日本の刑事訴訟における裁判員制度と異なり、米国の陪審制においては事実認定は原則として陪審員の専権であり、裁判官の役割は訴訟手続の運営と法の解釈適用、刑の量定等に限定されます。事実認定のための評議は、陪審員のみが参加して密室で行われます。
我が国の裁判員裁判においては、裁判官も評議に参加し、また有罪・無罪の判断をするには必ず職業裁判官がその判断に賛成していなければならないため、事実認定について職業的訓練を受けた裁判官が事実認定のプロセスに一定の影響、あるいは統制を与えることが予定されています。
他方で米国の陪審制においては、職業裁判官によるこのような事実認定の統制機能が発揮されないため、「陪審員による事実認定を誤らせる危険のある証拠を、いかにして排除する(=陪審員に見せない)か」という証拠法の役割がきわめて重要なものとなります。
では証拠法が対峙する(しなければならない)陪審員とは、どのようなものでしょうか。連邦証拠規則606条(b)*1に関する著名な米国連邦最高裁判決の反対意見中に描写された、極端な例をご紹介します。
*1 連邦証拠規則606条(b)(1)
「評決または正式起訴状の有効性に関する審理においては、陪審員は、陪審員の評議においてなされた発言もしくは当該評議において起こった出来事、当該陪審員もしくは他の陪審員の投票内容、または当該評決もしくは正式起訴状に関するいかなる陪審員の精神的変化についても証言することはできない。裁判所は、これらの事項に関する陪審員の宣誓供述書または陪審員の供述証拠を採用してはならない。」
タナー対合衆国
米国連邦最高裁判所 1987年6月22日判決
(Tanner v. United States, 483 U.S. 107, 107 S. Ct. 2739 (1987))
マーシャル判事の反対意見(ブレナン、ブラックマン及びスティーブンス判事が同調)
「…本件において主張されている陪審員の非違行為は、きわめて憂慮すべきものである。評決が下された数週間後、陪審員の一人、ヴェラ・アスベルは弁護人に連絡をよこしてきた。アスベルは、裁判中、数人の男性陪審員が飲酒し、そして『昼までずっと寝ていた』と述べた。アスベルによれば、ほかの陪審員(ティナ・フランクリン)も、このような行為があったことを認めるだろうとのことである。にもかかわらず、法廷意見や地方裁判所は、かかるアスベルの弁護人に対する供述は、連邦証拠規則606条(b)により排除されるとした。
数ヶ月後、アスベルの主張は、もう一人の陪審員ダニエル・ハーディによる、薬物やアルコールの乱用が陪審員間で蔓延していたという詳細な報告により、補強されることとなった。ハーディによれば、ハーディ本人を含む7人の陪審員は、昼休みにいつもアルコールを摂取していた。ハーディが報告するところでは、4人の男性陪審員は毎日、最大ピッチャー3杯のビールを分け合って飲んでいた。ハーディ自身『いつもアルコールを飲んでいた。』またハーディは、陪審員長をつとめた女性陪審員について、昼食に1リットルのワインを飲むような『アルコール中毒者』だと表現している。他の2名の女性陪審員も、昼食時に1、2杯のアルコールを飲んでいた。
さらに、この4人の男性陪審員の問題は、アルコールにとどまらなかった。彼らは『ほぼ毎日』マリファナを吸っていた。彼らのうち2名はときどきコカインも摂取していた。ときおり、2名の陪審員たちは全部―アルコール、コカイン、そしてマリファナ―を使っていた。ハーディはまた、最もひどい薬物使用者(「ジョン」と呼ばれている男)が、裁判中の休み時間にコカインを摂取していたと述べている。『私は彼がある仕掛けをしていて、トイレに行ったあと…まるで風邪でも引いたかのように…鼻をすすりながら戻ってくるのを見た』と。
ハーディの供述は、アルコールと薬物摂取の効果に関するアスベルの見立てを補強するものである。ハーディは、『陪審員のうちの多数又は数人が』『裁判中に居眠りをしていた』と述べる。少なくともジョンに関していえば、薬物とアルコールのため、裁判中起きていられなかった。」